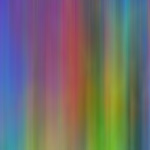那須高原の澄んだ空気を背負いながら、私は今日もまた新しいゴルフ場を歩いている。
40年近くゴルフ場運営に携わり、20を超えるコースを見つめてきた中で、ひとつの確信が生まれた。
ゴルフの上達には技術も大切だが、それ以上に「ゴルフ場を読み解く力」こそが、真のコースマネジメントの源泉なのだということを。
コースマネジメントの基本とは何か
朝霧に包まれたティーグラウンドに立つとき、多くのゴルファーは目の前の一打にだけ集中してしまう。
しかし、本当のコースマネジメントとは、もっと大きな視野で臨むものなのだ。
コースマネジメントとは、事前にコースレイアウトを確認したり当日の天候などを考慮して目標スコア達成のための戦略を練ることと定義されているが、私はもう一歩踏み込んで考えている。
それは、ゴルフ場という「生きた風景」との対話なのだ。
距離だけで測れないゴルフ場の個性
夕暮れ時のフェアウェイを歩いていると、同じ150ヤードでも、コースによってまったく異なる表情を見せることに気づく。
GPSが示す数字は同じでも、風の流れ、地形の起伏、芝の状態が織りなす条件は千差万別だ。
自分の能力、即ち、自分のショットの精度について より良い理解を持つことが 極めて重要なのは言うまでもないが、それと同じくらい大切なのが、目の前のコースが持つ個性を読み取ることなのである。
ティーグラウンドからグリーンまでの情報収集
私が支配人として勤めていた頃、キャディマスターからよく聞いた言葉がある。
「お客様は、ティーショットを打つ前に、既にスコアの半分が決まっている」
それほどまでに、事前の情報収集が重要だということだ。
ヤーデージブックに書かれた数字だけでなく、その日の風向き、グリーンの硬さ、ピンポジション。
これらすべてが、一打一打の判断材料となる。
「風・地形・芝」三位一体の読み解き
ゴルフ場を取り巻く自然の三要素が、風と地形と芝である。
芝をちぎってティグラウンド上を読む。ピンフラッグの揺れを確認する。ティグラウンド周辺の一番高い木の揺れを見るといった基本的な風の読み方に加えて、地形が風に与える影響も考慮せねばならない。
谷間のコースでは風が複雑に変化し、高原では一定方向から強く吹く。
芝目は昼間の太陽に向かって伸びるため、太陽の落ちる西側に向かって葉が伸びますという自然の摂理も、午後のラウンドでは重要な読み筋となる。
ゴルフ場という「風景」を読む
桜の季節、我孫子ゴルフ倶楽部の観桜会で多くの人々がコース内を歩く光景を見ていると、ゴルフ場がいかに美しい風景であるかを改めて実感する。
しかし、ゴルファーにとってのゴルフ場は、単なる美しい風景ではない。
そこには設計者の深い意図が込められた、戦略的な「読み物」としての側面があるのだ。
レイアウトに込められた設計者の意図
設計家を意識してプレーすると”あそこのバンカー、気になるでしょ”みたいな造り手の声が聞こえてくると語られるように、名設計家たちは単なる障害物を配置しているのではない。
彼らは、ゴルファーの心理を巧妙に読み、挑戦と報酬のバランスを緻密に計算してレイアウトを組み立てている。
アリソンが設計した東京ゴルフ倶楽部の18番ホールでは、ティーショットの着地点から見える光景が、まさに設計者の仕掛けた「問いかけ」そのものだった。
右のバンカー群は避けたいが、左に逃げすぎると次打でグリーンが狙えない。
この絶妙なジレンマこそが、コース設計の真髄なのである。
バンカーの配置に見る罠と導線
夕陽に照らされた白砂のバンカーは美しいが、その配置には冷徹な計算が隠されている。
多くのバンカーは、単純に「入れてはいけない場所」ではなく、「ここを意識することで、理想的なプレーラインが見えてくる場所」として機能している。
名門コースほど、このバンカーの「語りかけ」が雄弁だ。
ドライバーで飛ばしたい気持ちを抑えて、3番ウッドで確実にフェアウェイセンターを狙う。
そんな冷静な判断を促すのも、巧妙に配置されたバンカーの役割なのである。
季節・時間帯で変わる芝とグリーンの表情
実地プレーから得られる気づき(山下氏の実践方法)
私は新しいコースを取材する際、必ず朝・昼・夕方の3つの時間帯でグリーンを観察することにしている。
朝露に濡れたグリーンは重く、昼の日差しで乾いたグリーンは早い。
夕方になると、西日の影響で芝目の向きがさらに顕著になる。
同じグリーンでも、時間によってまったく異なる表情を見せるのだ。
観察のポイント:
- 朝:露の付き方で傾斜と芝目を確認
- 昼:日差しの強さでグリーンスピードを予測
- 夕方:西日が作る影で微細な起伏を把握
このような継続的な観察が、真のコース理解につながっていく。
名門と地方、異なる「読み解き方」
霞ヶ関カンツリー倶楽部のような名門コースと、地方の素朴なコースでは、求められる読み解き方がまったく異なる。
それぞれに独特の魅力と攻略法があるのだ。
名門コースに潜む伝統の意匠
関東七倶楽部は、関東にある7箇所の名門倶楽部として知られているが、これらのコースには共通した特徴がある。
それは、「時の試練に耐えた設計思想」が息づいていることだ。
100年近い歴史を持つコースには、単なる技術的な難しさを超えた、哲学的な深さがある。
フェアウェイの微妙なうねり、グリーンの絶妙な傾斜、そのすべてが長年のプレーヤーたちによって磨き上げられ、完成されてきた。
名門コースでは、「力任せ」は通用しない。
むしろ、コースとの対話を通じて、最適解を見つけ出す洞察力が求められる。
地方コースの変化と再発見
一方で、地方のコースには地方コースならではの魅力がある。
バブル期に造られた豪快なコースから、最近リニューアルされた戦略的なコースまで、多様性に富んでいる。
名門コースほどの格式はないかもしれないが、自然の地形を活かした素朴な美しさと、のびのびとプレーできる開放感がある。
また、地方コースは時代とともに変化し続けている。
経営の工夫によって新たな魅力を発見したコース、コース改造によって戦略性を高めたコースなど、「進化するゴルフ場」としての面白さがある。
例えば、神奈川県足柄上郡のオリムピックナショナル サカワコースの口コミを見ると、富士山を望む自然の地形を活かしながらも、コース改造により戦略性を高めた地方コースの魅力がよく表れている。
「読めるコース」「読ませないコース」の違い
長年多くのコースを見てきた経験から言えることは、コースには「読めるタイプ」と「読ませないタイプ」があるということだ。
読めるコースは、設計意図が明確で、正しい攻略法を見つければ必ず結果がついてくる。
一方、読ませないコースは、複数の選択肢を提示し、どれが正解かを最後まで明かさない。
どちらにも魅力があるが、読み解きの方法は大きく異なる。
前者では緻密な分析が、後者では柔軟な発想が求められるのだ。
コースマネジメント力を高める実践術
理論だけでは、真のコースマネジメントは身につかない。
実際のラウンドで実践を重ねることで、初めて本物の力が養われるのである。
ラウンド前のコース図チェック術
私が支配人時代にお客様によくお話ししていたのは、「コース図は地図ではなく、物語だと思って読んでください」ということだった。
各ホールには、設計者なりの「起承転結」がある。
- 起:ティーグラウンドからの第一印象
- 承:フェアウェイでの展開
- 転:アプローチでの転機
- 結:グリーンでの結末
この物語の流れを事前に理解しておくことで、実際のプレーでも冷静な判断ができるようになる。
プレースタイルと天候のマッチング
良いスコアを出す上で、良いショットを打ち続けることは必須ではない。いかにリスクを避けてプレーを組み立てるかという考え方が、天候によるコース戦略では特に重要になる。
雨の日のゴルフでは、普段のアグレッシブなプレーを封印し、確実性を重視する。
風の強い日には、風を利用したショットと風を避けたショットを使い分ける。
自分のプレースタイルを天候に合わせて調整することも、高度なコースマネジメントの一環なのだ。
自分の傾向とゴルフ場の癖を照らし合わせる
ゴルフには「相性」がある。
ドローヒッターにとって右ドッグレッグは有利だが、左ドッグレッグでは工夫が必要だ。
自分の球筋の傾向と、そのコースの特徴を照らし合わせることで、より効果的な戦略が立てられる。
傾向分析の要素:
- 持ち球の方向性(ドロー・フェード)
- 得意な距離帯
- 苦手なライやシチュエーション
- 調子の波のパターン
若手・女性ゴルファーに向けたアプローチ法
最近、孫と一緒にショートコースを回る機会が増えた。
そこで気づいたのは、若いゴルファーや女性ゴルファーには、従来とは異なるアプローチが有効だということだ。
古江彩佳選手は20歳とまだまだ若いけれど海外などの試合経験がとても豊富で、様々な状況を想定した練習を積んできて、引き出しの幅広さを感じさせますとあるように、現代の若手女性ゴルファーは、従来の「力で押し切る」ゴルフとは正反対の、洗練された戦略的思考を持っている。
彼女たちには、コースの「美しさ」と「戦略性」を同時に伝えることが重要だ。
技術的な解説だけでなく、そのコースが持つ歴史や設計思想も含めて説明すると、より深い理解につながる。
また、飛距離に頼らない攻略法を提示することで、ゴルフの奥深さを実感してもらえるのである。
まとめ
夕暮れのゴルフ場を歩きながら、私はいつも同じことを考える。
ゴルフとは、自然との対話であり、設計者との対話であり、そして自分自身との対話なのだということを。
コースを読むことでゴルフはもっと豊かになる
技術だけに頼ったゴルフは、どこか薄っぺらい。
しかし、コースを深く読み解くことができれば、ゴルフは格段に豊かなものになる。
一打一打に物語が生まれ、18ホールが一つの壮大なドラマとなる。
それこそが、真のゴルフの醍醐味なのではないだろうか。
ゴルフ場は現代の「道中」――山下修一の提言
司馬遼太郎の『街道をゆく』を愛読する私にとって、ゴルフ場はまさに現代の「道中」である。
そこには歴史があり、文化があり、人々の想いが込められている。
ただボールを打つだけでなく、その土地の風土や歴史に思いを馳せながらプレーすることで、ゴルフはスポーツを超えた豊かな体験となる。
Q:コースマネジメントで最も重要なポイントは何ですか?
A:自分の能力を正確に把握し、無理をしないことです。コースの誘惑に負けず、自分にとって最も確実な方法を選択することが、結果として良いスコアにつながります。
Q:名門コースと一般コースでマネジメントは変わりますか?
A:基本的な考え方は同じですが、名門コースでは設計者の意図をより深く読み取る必要があります。一方、一般コースでは自然の地形を活かした素朴な攻略法が有効な場合が多いです。
Q:コース攻略で風の影響を正確に読むコツはありますか?
A:ティーグラウンドの芝を散らすだけでなく、コース全体の木々の揺れ方や、グリーン周辺の旗の動きを総合的に観察することが大切です。特に高い木の上部の動きは、上空の風向きを知る重要な手がかりになります。
次世代とともに楽しむ、これからのコースマネジメント
孫との時間を通じて、私は新しい発見をしている。
若い世代は、我々とは異なる視点でゴルフ場を見つめている。
彼らの感性と、我々世代の経験を融合させることで、きっと新しいコースマネジメントの形が生まれるに違いない。
ゴルフ場という現代の道中を、次の世代とともに歩き続けていきたい。
そこにこそ、ゴルフの真の未来があるのだから。
最終更新日 2025年6月10日