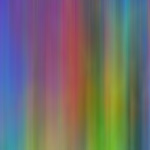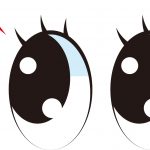永代供養とは
永代供養は家族が身寄りがない人にとって、代わりにお墓の管理が任せられる仕組みです。
具体的にはお寺や霊園が家族の代わりになって、お墓を見守り供養してくれるのが特徴です。
ただ永代という呼び方には誤解があり、必ずしも永久に管理が任せられるわけではないといえます。
実際のところは期限が設けられているので、永代供養といっても契約時に確認することが肝心です。
期限は17回忌や50回忌までなど、管理を引き受けるお寺や霊園によってまちまちです。
永久だと思っていたら期限付きで、更に17回忌で終わってしまうこともあり得ます。
安心してお墓に入る為には、自らが亡くなった後が大切なので、事前に確かめる必要があります。
一般的には33回忌が平均的な期限の目安で、以降は管理が行われなくなります。
しかし心配は無用で、契約を終えた後の遺骨は合祀に移されるので安心です。
合祀は他の人と一緒に埋葬される方法で、永代供養墓と呼ばれるお墓に移ります。
今後埋葬者が増えることを考慮すると、合祀という管理方法は現実的で、誰もが納得できる合理的なやり方です。
契約期間と同じく合祀にも基準や決まりはなく、遺骨の保管先を骨壷と土に分けたり、全て土に埋めるなど様々です。
他人と同じお墓に入れられるので、抵抗感は生じるかもしれませんが、身寄りがなく放置されるよりは遥かにましです。
(参考)
永代供養墓「我逢人」 – 横浜あおば霊苑
永代供養と永代使用は異なるので注意
永代の呼び方は安心感を与えますが、同時に永久に管理してくれるといった誤解を生んでいます。
加えて永代使用という似た言葉もあるので、誤解は更に誤解を呼びます。
永代使用は予め費用を支払うことで、お墓の利用権を獲得したり使用できることを指します。
土地の利用料金とも言い換えられるので、意味合いとしては大きくことなります。
一方の永代供養では、いくつかのタイプに分かれて選択できるようになっています。
埋葬には屋内型と屋外型があって、前者は納骨堂と呼ばれる施設で管理されます。
管理設備は可動する収納設備やロッカー型など様々で、土に遺骨を埋めて墓を建てるイメージとは異なります。
イメージは墓地と掛け離れていますが、管理を行う人が見守ってくれるのは確かです。
費用について
費用は施設の維持費と相まって、数万円から数百万円といったところです。
屋外型には納骨壇や納骨塔、それに合祀型という主に3つの種類があります。
納骨壇は個別に遺骨の安置を行う方法で、一般的なお墓に近い管理が行われます。
他人と遺骨が交じることはないので、一人静かに過ごしたい人に向いています。
個別に遺骨が安置されることから、個人のアイデンティティを守れますが、管理の手間が増える分だけ費用も増加します。
納骨塔型は塔を目印として、地下で遺骨をおさめたり管理する方式です。
こちらは合祀される傾向が強いタイプで、比較的費用が安く済みます。
合祀型は遺骨を一ヶ所に集めて埋葬するやり方で、イメージとしてはやや大雑把です。
管理の手間が少なくコストが掛からないことから、安価な永代供養の選択肢となっています。
結果的に希望者が集まりやすく、多くの人達と埋葬されることになります。
安置法にも複数の種類がある
屋外型には3種類の分類がありますが、安置法にも複数の種類が存在します。
墓石安置は一般的なお墓がベースで、管理方法が変わったタイプのことです。
お墓を見守る家族が居なくなった場合、お寺や霊園が代わりに管理してくれるようになります。
違いは管理方法だけなので、通常のお墓に入れるという安心感が得られます。
合祀型は料金が低い代わりに、他の遺骨と一緒に埋葬されることになります。
合祀の仕組み上、一度埋葬された遺骨を取り出すことは不可能なので、良く考えて決めることが重要です。
分骨や改葬は事実上できなくなりますから、その点が注意すべきポイントです。
また合同墓とも呼ばれていて、合祀がよりイメージしやすくなっています。
個別安置型も墓石は建てられますが、墓石安置型とは違い、一定の期間を経てやがて合祀されます。
33回忌や50回忌までは個別に遺骨が安置されるので、暫くの間は分骨や改葬できる余地が残ります。
単純な合祀と集合安置型の違いについて
集合安置型は一ヶ所に遺骨が集められるものの、個別に骨壷の用意が行われるので、混ざらない点が単純な合祀との違いです。
石碑も一人分ずつ用意されるので、アイデンティティを守ることができます。
勿論分骨も改葬も可能ですから、後で家族が遺骨を管理できるようになっても対応が行えます。
お墓を管理する人がいなくなった時、永代供養はなくてはならない選択肢になります。
ただしその方法には一長一短があって、管理の手間が増えるほど費用が上がる傾向です。
中には分骨が難しくなるケースもあるので、選択には細心の注意を払うことが必要です。
逆にお墓の管理に関する先行きが不安であれば、デメリットを踏まえても選ぶ価値が高まります。
予算に余裕がある、あるいは将来的に家族が管理をしてくれる場合は、合祀されない埋葬を選ぶ方法もあります。
選ぶ側に選択の余地がありますから、特徴を踏まえたり理解して、比較しながら絞り込み選ぶことがポイントとなります。
最終更新日 2025年6月10日