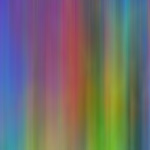1.日本赤十字社とは
日本赤十字社は赤十字運動で知られる国際赤十字、赤新月運動によって運営が行われている、日本の赤十字社です。
1952年に制定された日本赤十字社法に基づき、同年8月14日付けで設立された認可法人です。
国内では日赤や赤十字と呼ばれ、これらの略称で親しまれている組織となっています。
企業ではありませんが、組織を理解したり賛同する人達のことを社員と呼びます。
実際は会員や仲間といったニュアンスで、年間500円以上の協力を行うと一員になれます。
参加は個人も法人でも可能となっており、長野県だけでも既に30万人もの社員数に達しています。
社員はあくまでも活動の参加が意義ですから、会員特典のようなものはないです。
活動の参加はなく、協力という形で支援をしたいならば、寄付金で日本赤十字社の力になることが可能です。
活動に取り組む義務はありませんし、お金で人道的事業に役立てられますから、興味を持ったら一考の余地ありです。
この社員制度は現在の組織の前身、博愛社の創立にまで遡ります。
1877年には既に存在していましたから、それだけ今も重要な呼び方や仕組みだといえるでしょう。
日本における同組織のルーツは、西南戦争が行われていた明治10年、1877年に熊本洋学校に設立された博愛社です。
佐野常民は戦争の悲惨な状況を考え、陸軍省に対し敵味方に関係なく救護を行う救護班の派遣を願い出ます。
しかし、陸軍卿を代行する西郷従道により、内戦は国家間の戦争と違い赤十字の救護対象ではないと断られます。
佐野は征討総督を務める有栖川宮熾仁親王の元に出向き、救護班の派遣を願い出て認められることになります。
逆徒でも天皇の臣民の敵も救護するという、その博愛精神を良しとして、博愛社の設立認可に至るわけです。
これが日本における日本赤十字社発足のルーツで、現在にも受け継がれている精神の1つです。
2.1887年に博愛社から日本赤十字社に名称変更
ただ、当時は敵味方に関係なく助ける思想が一般に受け入れられず、妨害を受けたり死者が発生したのも確かです。
博愛社が今の名称に改名されたのは、ジュネーヴ条約に政府が調印した1886年の翌年、1887年のことです。
改称と同時に特別社員や名誉社員制度が新設され、近代化を目指す当時の日本においては、明治天皇皇后も積極的に活動に参加しました。
西欧の皇室や王室では、赤十字活動に盛んでしたから、その影響を受けた結果が当時の日本だったといえます。
紋章の赤十字竹桐鳳凰章は、昭憲皇太后の宝冠のデザインが模倣され制作や制定が行われています。
1888年になると、福島県の磐梯山で巨大な水蒸気爆発による大災害が発生しました。
国際紛争解決を目的とした当時の赤十字でしたが、自然災害でも活動できるように政府に願い出します。
前例がない戦時外の活動ですが、政府の了解により救護班が現地に派遣され活動を行っています。
今もトルコ人の心に残り日本との関係に根強く存在している、1890年のエルトゥールル号遭難事件の救護班派遣も印象的です。
500名以上の遭難を出した大事件でしたが、日本人の活躍によって69名が救出され生還できています。
トルコと日本はとても離れていますが、この事件を切っ掛けに両国の関係は近くなり、現在でも慰霊祭や追悼式典が行われます。
3.看護師を養成する大学や専門学校もある
戦争で初めて本来の活動に取り組んだのは、1894年から1895年の間に発生した日清戦争です。
国際紛争の医療救護班として戦地に送り出され、歴史に新たな記録を残しています。
日露戦争ではロシア人を、第一次世界大戦ではドイツ人をそれぞれ援助しました。
1914年から1918年の間には、連合国のフランスとイギリスやロシアから要請を受け、参加国にそれぞれ救護班を派遣しています。
1920年のロシア革命によるポーランド孤児救済や、1959年の国内外における戦争や紛争の救護活動など、日本赤十字社の活躍は多岐にわたります。
その後は各都道府県支部に病院や診療所を始めとして、血液センターと献血ルームや福祉施設などが設立されました。
看護師を養成する大学や専門学校もありますから、組織や社会貢献の大きさが伝わってきます。
日本赤十字社には奉仕団という存在があり、思想や目的に賛同するボランティアで構成されています。
普段は支援活動を行っていますが、災害時になると無給で救援活動に参加する人達です。
地域組織に根づく地域と、学校単位で学生が構成する青年、そしてアマチュア無線やスキーヤーなど、特殊技能者で構成される特殊の3種類に分けられます。
いずれも災害や緊急時に能力を活かす赤十字のメンバーですから、日本ユニセフ協会などその他の組織とともに社会を陰ながら支えている存在だと考えられます。
このような仕組みも合わせて、日本の赤十字は独自に組織づくりや活動を行い、誕生から今に至るまで長い歴史を作り上げています。
最終更新日 2025年6月10日